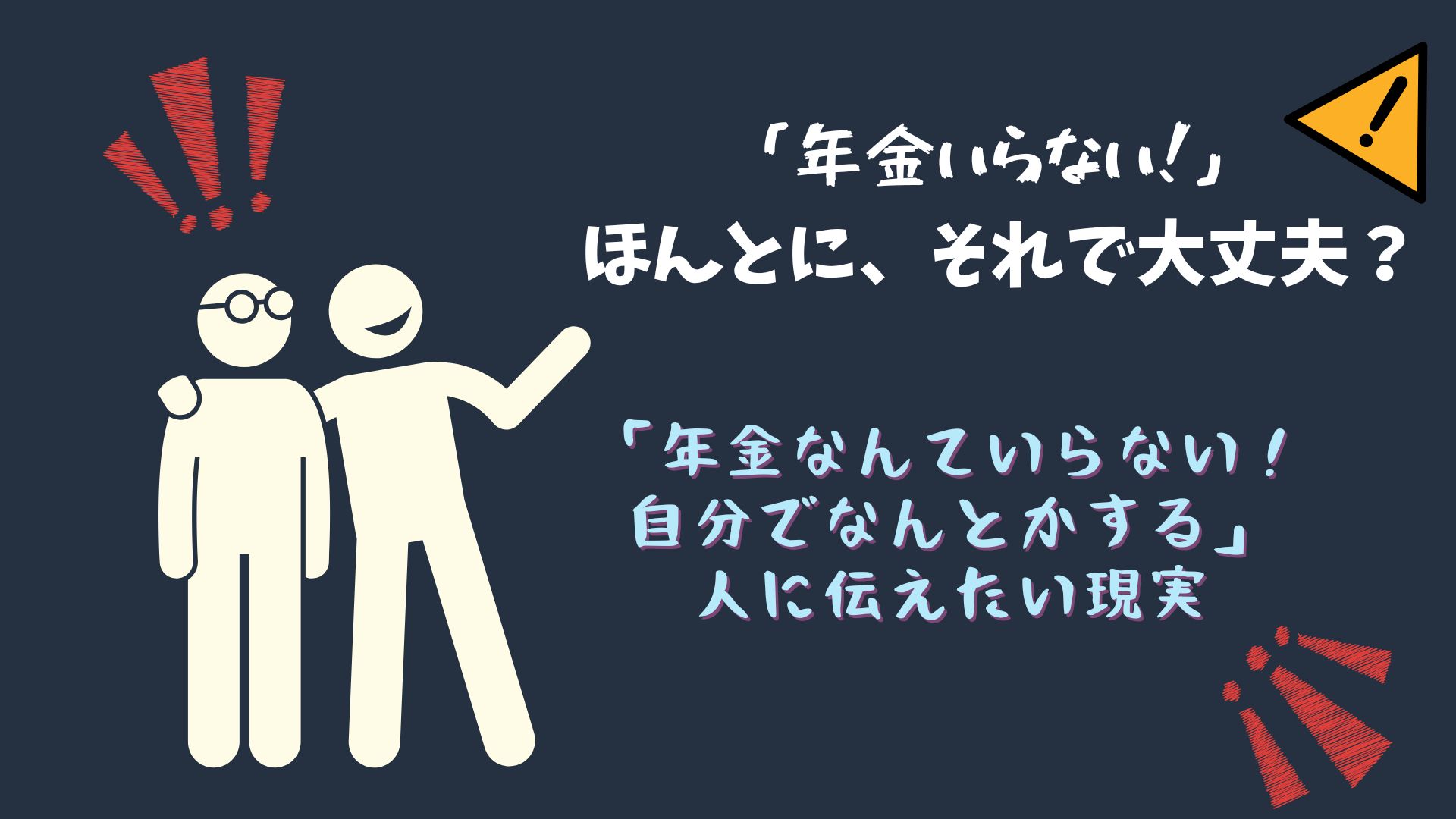「自力で備える」という考え、否定はしません
最近よく聞くのが、
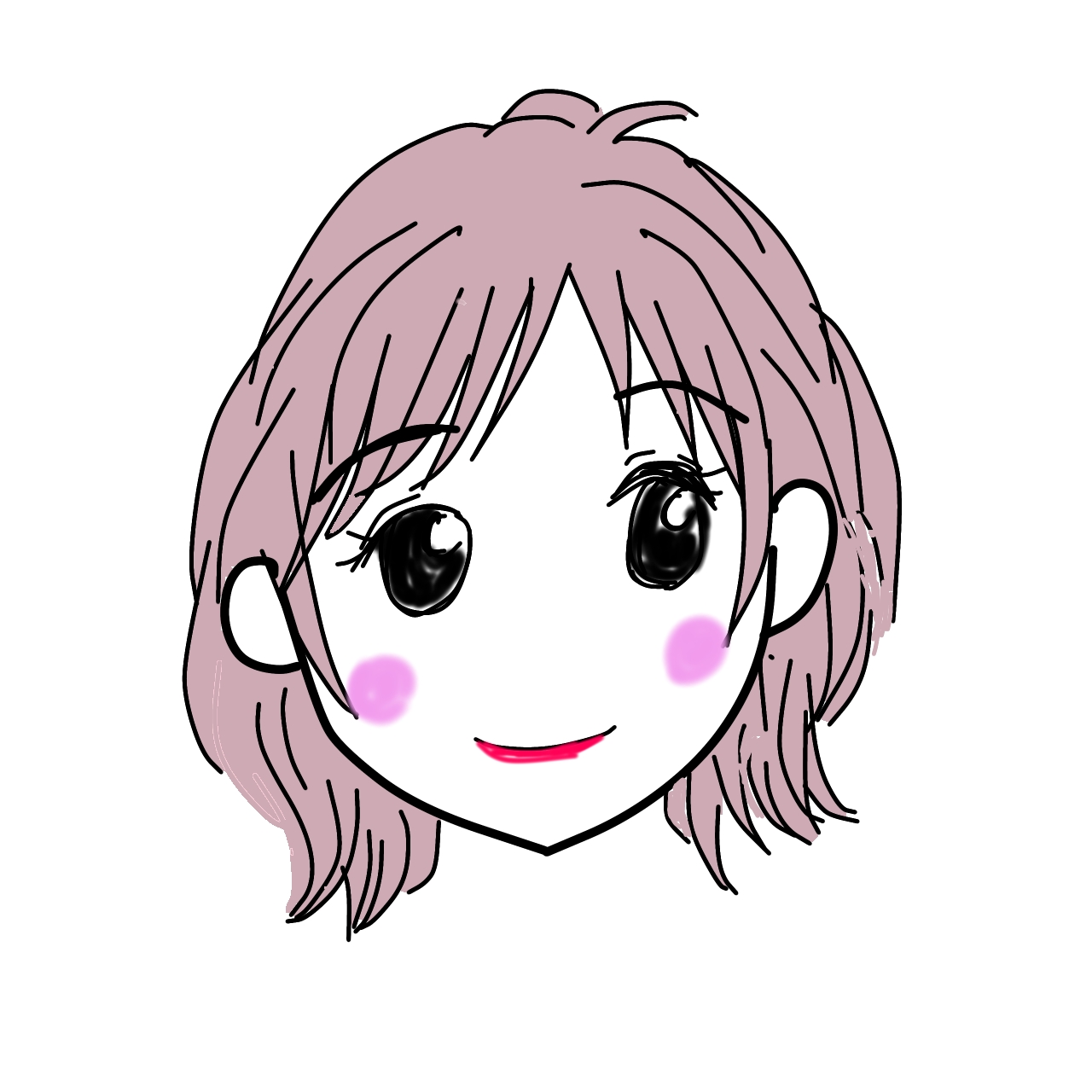
年金なんてどうせもらえないんでしょ?
自分で資産形成すればいいよ。
という声。
特に20代〜40代の若い世代に多い印象です。
確かに、国の制度に100%頼ることに「不安を感じる気持ち」
とても理解できます。
でも、私はこう考えています。



だからこそ“最低限の公的年金”を押さえた上で、
“自力で備える”のが賢い選択
だと。
今日は、「年金いらない、自力で全部やる!」という考え方が実はかなりリスクが高いということを、データをもとにお伝えしたいと思います。
📉 年金ゼロで老後を迎えるなら、6,000万円以上の備えが必要
まずシンプルに、老後に月20万円の生活費が必要だとした場合。
65歳から90歳までの25年間で必要な金額は…
これを30歳から60歳までの30年間で準備するには、毎月約104,000円の積立が必要です。
もし20歳から始めて60歳までの40年間で準備する場合は、毎月約65,000円の積立額が必要です。
これは会社員の方でも結構きつい水準ですよね☹️💦
つみたてNISAやiDeCoで資産形成をしている方でも、この金額に到達するのはかなりの計画性と継続力が必要です。
年金は「老後資金」だけじゃない
むしろ“保険”です
もうひとつ忘れてはならないのが、公的年金には「老後のお金」だけでなく、
- 障害を負ったときの【障害年金】
- 家族を残して亡くなったときの【遺族年金】
といった人生の“もしも”に備える保険機能がついているということです。
民間でこれをカバーしようとすると以下の費用が発生します。
| 保険の種類 | 月額保険料(30代の場合の目安) |
|---|---|
| 就業不能保険(障害対策) | 約2,500円 |
| 定期生命保険(遺族対策) | 約1,500円 |
| 医療・がん保険 | 約4,000円 |
| 合計 | 月8,000円以上 |



つまり、「年金には入らないけど、もしもに備える」なら、月8,000円以上は自分で払う覚悟が必要になります。
民間保険と公的年金の違いも知っておきたい
| 比較項目 | 公的年金 | 民間保険 |
|---|---|---|
| 加入制限 | 誰でも加入可 | 審査あり(持病や年齢で不可も) |
| 保障期間 | 原則“終身” | 有期・更新制あり |
| 保険料 | 所得に応じて変動 | 固定額(年齢・性別で変動) |
公的年金は「万人のための保険」であり、誰でも・いつでも・一生涯保障される仕組みです。
それにたいして、民間はあくまで“補助的役割”です。
わたしのおすすめは「ハイブリッド戦略」
「年金を信じる」「信じない」ではなく、制度の仕組みを理解したうえで、
公的年金+自助努力(iDeCo・NISA・民間保険)をうまく組み合わせる
これがいちばん安定して、しかも現実的な方法だと思っています。
公的年金だけだといくらぐらいもらえる?
2025年度時点での年金受給目安(満額支給の例)です。
| 種別 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|
| 国民年金(基礎年金) | 約80万円 | 約6.6万円 |
| 厚生年金(平均年収500万円) 加入者 | 約150万円前後 ※国民年金(基礎年金も含め) | 約12.5万円 |
📌 厚生労働省のデータでは、老後夫婦2人世帯で1ヶ月に約28万円前後の金額が必要となっていますが、家賃や医療費、インフレを考えると心もとない金額です💦
公的年金+自助努力(自分で準備)=老後の安心
① iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 自分で積み立てて運用、60歳以降に年金として受け取り
- 掛金が全額所得控除され、節税効果も大
- 原則60歳まで引き出せない=老後資金に確実に回せる
② NISA
- 利益に税金がかからない
- いつでもお金を引き出せる
- 投資信託や株式などで長期的な資産形成が可能
- 65歳以降も積立OK
③ 国民年金基金/小規模企業共済(自営業向け)
- 自営業者やフリーランスの老後の「2階建て」年金
- 掛金が全額所得控除の対象



今から積み立てる人が、一番得をする時代ということです。
積立方法は、いろんなパターンがるので、ネットなどで試算しても良いと思います。
🎓 まとめ
:制度を知ったうえで、“使いこなす”力を持とう
「自力でなんとかする」は、素晴らしい姿勢です。
でも、すべてを自己責任で背負うには、相応のリスクとコストがかかることを、ぜひ知っておいてください。
一方で、公的制度をうまく使えば、最低限の生活保障を“ほぼ自動的に”得ることができます。
「制度を知り、必要なものだけを選び取る」
それがこれからの時代の“強くてしなやかな生き方”ではないでしょうか。